ETFの経費率の低さにこだわりたい理由
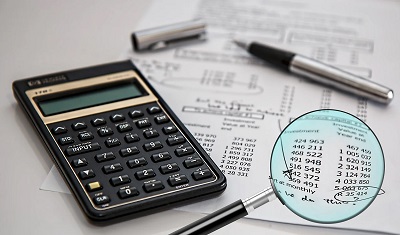
こんばんは、いなかのです!
今回は、どうして「ETFの経費率に拘るのか」を実際のETFの経費率に当てはめて計算し紹介していこうと思います。
基本的にETFの経費率は低く抑えられていますが、コストの安さを求める理由を実際に数字で見ると印象が変わってくると思うので、計算しながら見ていきましょう。
本記事の計算はあくまで目安として捉えてくれたらと思います。
ETFに掛かるコスト
主にETFを購入・保有する際に掛かるコストは以下の二つに分類されます。
1.売買手数料
2.保有手数料(いわゆる信託報酬)
経費率とは、「ETFを運用するために必要な費用が、ETFの純資産額に対してどのくらいの割合なのか」を表したものです。
経費率の中身は「有価証券の売買委託手数料、保管費用」などが含まれますが、主な経費は「信託報酬(保有している間かかるコスト)」になります。
そのため、経費率0.04%のETFはあれば実態内訳は管理手数料0.03%+その他0.01%で0.04%となりますが、
今回の記事では分かりやすく経費率0.04%は信託報酬0.04%で計算させてください。
※1年に1回決算のあるETFの場合、期末時点で純資産額100億円、1年間にかかった経費の合計が2億円であれば、経費率は2%となります。
1.売買手数料について
売買手数料は、ETFの購入時と売却時に掛かる手数料の事です。国内ETFは国内株式手数料、海外ETFは外国株式手数料に準じています。
例えば、SBI証券は米国ETFであれば買付手数料は1注文あたりの約定代金×0.45%(税込0.495%)になっています。
証券会社毎に手数料は異なっており、該当商品によっては(基本的に投資信託・ETF等)買付手数料が無料、解約手数料が無料等もあります。
2.保有手数料(信託報酬)について
信託報酬とは、ETF(投資信託)の信託財産から毎日一定の割合で差し引かれる費用のことで、ファンドの運用会社・販売会社および、ファンドの運用資産を保管・管理する信託会社に分配される費用を指しています。
ETFの信託報酬は365日間払い続けているコストであり、金額は純資産額に対する比率(年率)を日割りにして、基準価格から引いていきます。
例えば、投資金額が10万円で、信託報酬が1.5%の場合、365日保有した場合、信託報酬は10万円×1.5%×365/365=1500円の信託報酬が掛かります。
もし10万円の運用資産が全く増えなかった場合、10万円ー1500円=98500円の運用資産となります。
ETF毎の信託報酬の計算
ここからは実在するETFで信託報酬の計算をしていきます。
ただし、毎月5万ずつETFを購入した場合や、数か月おきに10万ずつ購入のような事例に対して正確に信託報酬を出すのは非常に困難です。
そのため、初めに基準価格100万円のものを100万円分を購入し、そのまま資産額が動かなかった場合に発生する信託報酬を出すことにします。(そんなことありえないのですが、あくまで目安としてみて頂ければ。)
①1年間のコスト
100万×0.07%×365/365日=700円
②1日あたりのコスト
100万×0.07%×1/365日=1.9円
③10年保有した場合
700円×10年=7000円
①1年間のコスト
100万×0.03%×365/365日=300円
②1日あたりのコスト
100万×0.03%×1/365日=0.821円
③10年間保有した場合
300円×10年=3000円
上記の経費率0.07%と0.03%の例を見て頂きました。そもそも0.1%切ってる破格のコストなので10年保有見てもこんなもんならってなってしまいますね。
ということで↓では経費率1.5%で見てみましょう。
①1年間の保有コスト
100万×1.5%×365/365日=15000円
②1日あたりのコスト
100万×1.5%×1/365日=41円
③10年保有した場合
15000円×10万=150000円。
と途端にコストが膨れ上がります。
この数値ですと1年間ですら無視できない数値になってくるのが分かります。
これが、可能ならば経費率が抑えられているETFを選んだ方がいい理由になっています。
世界三大運用会社のETFは基本的に低コスト
世界三大運用会社である、ブラックロック、バンガード、ステートストリートのETFは基本的に低コストとなっています。
特にETFの資産規模が世界最大級になっているバンガードのETFは経費率が低コストで日本でも有名です。
話によれば、バンガードの運用ファンドはバンガードが所有しているものだからだとか。(ここら辺はちょっと他社を調べ切れてないので無視してください)
また、バンガードのETFは定期的に経費率が見直される傾向にあり、例えばVUGは規模が大きくなるにつれ0.1%→0.06%→0.04%のように経費率が見直されました。
バンガード(設立1975年)

バンガードのETFで人気の高いETFはS&P500連動のVOO、米国株式市場の小型株~大型株に投資するVTIです。
どちらも経費率が0.03%となっています。
VTという先進国と新興国つまり全世界の株式を取りこんだETFも人気が高いです。経費率は0.08%とこちらも全世界に投資するという手間のわりにかなり低く抑えられています。
ブラックロック(設立1988年)

ブラックロックは投資家の投資目的に合わせたETFを提供してくれています。
また、ESG(環境・社会・ガバナンス)にいち早く目をつけたのはステートストリートなのですが、ブラックロックは公式HPで大々的に謳っておりESGを最重要視している点が今後の運用パフォーマンスに大きな差が出る要因になってくると私は見ています。
ブラックロックのETFを見るとS&P500連動のIVVで経費率0.03%です。
また、直近分配金▼0.77%の減配で抑えた高配当ETFのHDVですら0.08%と低コストです。
ステートストリート(設立1978年)
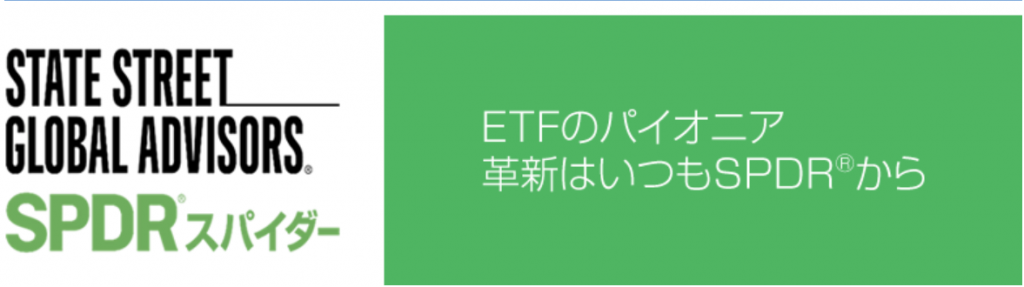
ステートストリートはETF大国の米国で初めてETFを発売した企業です。
米国第一号のETFであるSPDR®S&P500®ETF(SPY)は2018年1月29日に米国上場25周年を迎えています。
SPYはS&P500連動のETFであり経費率0.09%と他社に比べ高めの設定になっています。
皆さんご存じのSPYDの経費率は0.07%。
また、グロース株ETFとして好調なSPYGは0.04%とステートストリートも低コストのETFが多くあります。
私が勝手にそう呼んでいるセクターETFのXシリーズ達は経費率0.13%が目印になります。
まとめ
①経費率は(売買手数料+信託報酬+その他)の事
②信託報酬の高さは長期保有になるほど無視できなくなる
③世界三大運用会社ETFの経費率は低い
重ねていいますが、経費率とはETF全体に掛かるトータルコストの事を指します。
ステートストリートの公式HPを見ると、総経費率という書き方をしてくれているのでトータルコストというイメージが湧きやすいです。
また、どの運用会社でも言える事なのですが、投資先が専門的・特殊であればあるほど経費率は高くなります。
それは運用する上でより緻密な作業が必要になるためです。
指数連動を目指すだけのETF、いわゆるインデックス投資というのは指数に投資をするので、銘柄選定の調査の手間が省ける分、コストを抑えることが出来るということです。
今回はETFの経費率と世界三大運用会社について書きましたが、運用会社はまだ他にもありますし、ありとあらゆるETFが存在します。
是非自分の好きな運用会社で好きなETFを見つけてみてください。
関連記事
↓バンガードのVOOに投資が出来る投資信託について。
↓ブラックロックの財務健全性を重視した高配当ETFのHDVについて
↓S&P500銘柄のグロース株を厳選して投資ができるETF:SPYGについて













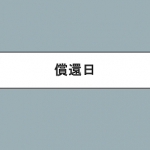







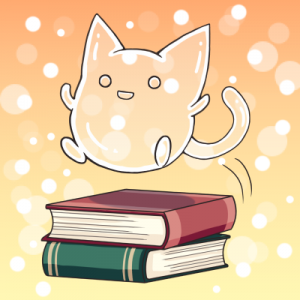
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません